珪藻土とは

【珪藻土(けいそうど)】
1. 概要
「珪藻土」とは、太古の植物プランクトン(珪藻)の死骸が海底や湖底に堆積し、化石化した土(堆積岩)のことです。
最大の特徴は、目に見えない無数の微細な孔(あな)が開いた「多孔質(たこうしつ)」構造である点です。この孔が呼吸するように湿気やニオイを吸着するため、漆喰(しっくい)と並んで人気の高い左官(さかん)塗り壁材です。
(※塗り壁材としては、珪藻土そのものは固まる性質がないため、石灰や粘土、合成樹脂などの「つなぎ材(凝固材)」を混ぜて使用されます。)
2. メリット
-
優れた調湿性: 空間の湿度が高くなると無数の孔が湿気を吸収し、逆に空間が乾燥すると内部の湿気を放出します。この「呼吸する」性質により、室内の湿度を快適な状態に保ちやすく、結露やカビの発生を抑制する効果が期待できます。
-
高い消臭性: 湿気だけでなく、ニオイの分子も吸着します。ペットのニオイ、タバコ臭、玄関やトイレのアンモニア臭など、生活臭を軽減する効果があります。
-
防火性: 主原料が土(無機物)であるため、不燃性で火に強く、防火性に優れています。
-
独特の質感: 漆喰がツルッとした仕上げが可能なのに対し、珪藻土はザラッとした、マットで素朴な風合いに仕上がります。ナチュラルテイストや和モダンな空間と特に相性が良いです。
3. デメリットと注意点
-
コストと工期: ビニールクロス(壁紙)の張り替えと比べ、左官職人の手作業による左官工事となるため、材料費・工事費ともに高額になり、工期も長くなります。
-
もろさ(傷・粉落ち): 表面が比較的柔らかく、物を強くぶつけると削れたり、傷がついたりしやすいです。また、つなぎ材の種類によっては、手で触ると粉が落ちやすい製品もあります。
-
汚れ・シミ: 吸水性が非常に高いため、コーヒーや醤油、油などが飛ぶと瞬時にシミになってしまい、落とすのが困難です。水拭きができない製品が多いため、掃除にも注意が必要です。
-
施工場所: 水が直接かかる場所(浴室の壁など)や、油汚れが飛びやすいキッチンコンロ周りへの施工は原則として不向きです。
4. リノベーションでの活用
その高い調湿性と消臭性から、リビングや寝室のほか、湿気がこもりやすいウォークインクローゼット(WIC)やシューズインクローゼット(SIC)、廊下などの壁・天井に採用するのが特におすすめです。
5. 関連語
珪藻土の関連記事
-

実家を1000万円でリフォーム|工事範囲と価格目安、施工事例を徹底解説
「古くなった実家をリフォームして住みたい」「相続した実家を改……
2024.09.05 -

家を自分でリノベーションするメリット・デメリットは?プロが教える難易度や注意点
「DIYで自宅をリノベーションしたい」「自分でリノベ……
2023.11.15 -

〈憧れの海外高級マンション〉内装リフォームのポイントは?事例紹介も
海外のゴージャスな高級マンション風な内装に憧れる方も……
2023.09.24 -

マンションリノベーションに自然素材を!おすすめ素材や事例写真を紹介
「自然素材の家」と聞くと、木造住宅を連想する方が多いかもしれ……
2023.02.06 -

和風リノベーションは“和風モダン”がおすすめ!15のポイントを解説
ご自宅のリノベーションをご検討中の方にとって、どんなデザイン……
2023.02.01 -

内装リフォームビフォーアフター8選|マンション・一戸建て
この記事では、マンション・一戸建てそれぞれの内装リフォームビ……
2023.01.18

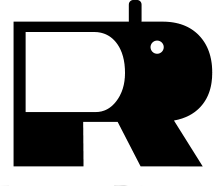












 電話で相談
電話で相談