公開日:2024-01-21 更新日:2025-04-22
親名義の実家をリノベーション|住宅ローンや税金など“お金”に関する注意点
「実家をリノベーションして親と一緒に暮らしたい」
「親のリタイアを機に二世帯住宅へリノベーションしたい」
そうお考えの方も多いでしょう。
しかし、親名義の実家をリノベーションする際、注意しなくてはいけない点や、事前に把握しておかなくてはいけない点があります。
そこで、今回はローンや税金など“お金”に着目して、押さえるべきポイントを紹介します。
ご実家のリノベーションを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
・実家の所有者とリノベーションの費用を負担する人が異なると、思わぬコストがかかる可能性があります。
・実家をリノベーションするには、計画段階からの綿密なシミュレーションが重要です。
・実家をリノベーションするなら、税制面やローン、売却の可能性も含めて総合的に相談できるワンストップリノベーション会社がおすすめです。
目次
親名義の実家を子のお金でリノベーションする場合は要注意
「両親が住んでいる実家が古くなったので、親孝行でリノベーション費用を負担したい」「フルリノベーションして将来自分たちが住む時に備えたい」そうお考えの方も多いはずです。
特に、地価の高い東京都心部などでは、その傾向は顕著でしょう。
しかし、ご両親の所有している実家をお子さんが費用を負担してリノベーションする場合、コスト面で不利になる可能性があります。
住宅所有者とローン契約者が違うとローン控除対象外に
通常、住宅ローンの融資を受けて中古住宅を購入したり、特定のリノベーションをすれば、「住宅ローン控除」が受けられます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、年末調整を行うことで一定期間、所得税額の一部が控除される制度です。(参考:国土交通省|住宅ローン減税)
そのため、実家の場合もバリアフリー工事や省エネ工事をすれば、控除対象になると思うかもしれません。
しかし、残念ながら、あくまでも対象は「自己の保有かつ居住の用に供する住宅」に限定されるため、いくら身内が所有する住宅であっても、控除要件から外れてしまいます。
贈与税の支払い義務が発生する可能性も
ご自身が住むためのリノベーションであっても、その家の所有者がご両親であれば、民法上はリノベーションによって付加された部分も住宅の一部としてみなされます。
これを付合(ふごう)と言い、民法でその定義が明確に決められています。
第242条「不動産の付合」
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
(引用:民法)
つまり、家に付属する設備や内装は、全てその住宅所有者の所有物になるということです。
そのため、お子さんが多額の費用をかけてリノベーションした場合、その費用は子から親への“贈与”とみなされ、額によっては贈与税の支払い義務が発生してしまいます。
贈与税は、「暦年課税」と呼ばれる計算方法で算出され、1人につきその年の1月1日から12月31日までで贈与された金額から基礎控除額110万円を引いた額に課税されます。(参考:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合)
贈与税の基礎控除額である110万円以下のリノベーション工事であれば、家の所有者と工事費を払う人が異なっても、贈与税は発生しません。
実家リノベーションの諸経費を抑える方法
ご実家をリノベーションする際に、リノベーション費用以外の出費はできるだけ抑えたいですよね。
そのためには、「住宅ローン控除が対象外になる」点と「贈与税の支払い義務が発生する」点を解決しなくてはいけません。
では、具体的な解決方法を紹介します。
親から子へ実家を売却(譲渡)して名義変更する
最もシンプルで有効な方法が、親から子へ家を売却して名義変更する方法です。
これを法律上は「譲渡」と呼びます。
住宅ローンやリノベーションの対象となる建物分だけ所有権を移せば良いので、土地はそのまま親が持ったままでも問題ありません。
家屋は、築年数が経てば経つほどその価値が下がるため、既に古くなったご実家でしたら、固定資産評価額と同等の最低金額でも売買が成立します。
住宅の所有権が子に変更されれば、住宅ローン控除を受けられる可能性が高まりますし、リノベーション規模を問わず、贈与税の支払いは発生しません。
まだ築年数の浅い住宅など、固定資産評価額が高く、3,000万円以上の価値が付いた場合、売主である親に「譲渡所得税」が課せられる可能性があります。(参考:国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき))
また、売買金額は買主と売主で決められますが、極端にその価値より低い価格で取引すると、“贈与”とみなされて贈与税が発生するリスクもあるため、注意してください。
親から子へ実家を贈与して名義変更する
金銭のやり取りをせずに名義変更のみ行う方法を「贈与」と言います。
一般的に、築年数が経ち資産価値が低下した不動産を親から子へ贈与した場合、その課税対象額が少なくなります。
前述のように、名義変更前に子が親名義の実家をリノベーションをした場合は、リノベ費用分が親への贈与とみなされて課税対象になる可能性があるのですが、リノベ前に親から子へ名義変更をしておけば、大幅に贈与税額を抑えられる可能性があるのです。
万が一、住宅の価値がそれほど下がっていない場合は、救済措置として「相続時精算課税」という制度が設けられています。
この制度は、60歳以上の親(祖父母)から、20歳以上の子(孫)へ住宅などの資産を生前分与する場合に利用でき、贈与額が2,500万円以下であれば、“一時的に”贈与税が非課税となります。(参考:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合)
“一時的に”と言った理由は、贈与した人が亡くなったときには、他の相続財産と合計して相続税が計算される点にあります。
国税庁の行った調査によると、2021年に相続税を支払うこととなった人は、全国で「294,058名」にまで上り、その数は年々増えているのが現状です。
そのため、実家の贈与を受ける場合は、将来支払う可能性がある相続税も想定して、十分検討してください。
一般的には、売買(譲渡)による名義変更が税制面で最も有利と言われています。
なぜなら、親に課税される可能性のある譲渡所得税は、マイホームの場合3,000万円控除されるからです。
ただし、控除額を大幅に超える住宅ですと、贈与して相続時精算課税制度を利用し、将来、贈与税よりも控除制度が充実している相続税を払う方が、出費を抑えられる可能性があります。
※贈与税率:一律20%
※譲渡所得税率:15%(譲渡者が5年以上住んでいる場合、基礎控除額3,000万円以上の額が対象)
※相続税率:20%(相続額が3,000万円超から5,000万円以下の場合)
親子の共有名義に変更する
事例を見る:Case166「Design & Function」
二世帯住宅へリノベーションする場合、実家の所有権を一部のみ子へ移転する方法もあります。
子が負担するリノベーション費用と実家の不動産価格を照らし合わせ、リノベーション費用に相当する割合の不動産所有権のみを子へ変更するのです。
この方法をとれば、住宅ローン控除の対象から外れたり、贈与税の課税義務がなくなったりする可能性が出てきます。
ただし、古い実家ですと、固定資産評価額がリノベーション費用を下回っている可能性が高く、その場合はこちらの方法ではあまり意味がありません。
また、ご兄弟がいる場合に、相続の際に揉める原因となる可能性もあります。
そのため、共同名義に変更する際は、ご家族で十分話し合ってから決断してください。
親がリフォームローンを組む
まだご両親が働いている場合は、お子さんではなく親御さんがリフォームローンを組める可能性もあります。
この場合は、ご自身の家をご自身の負担でリノベーションすることになるため、住宅ローン控除や贈与税の問題はそもそも発生しません。
ただし、「親が契約者で実際に返済しているのは子」という方法には、リスクがあります。
ローンを契約者ではなくその他の人が負担した場合、負担してもらった金額は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があるためです。
ご両親がやむを得ずローンを返済できなくなった場合、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」と認定されれば、贈与税の課税対象から外れるかもしれません。
そのため、「どうしても子が支払わなくてはならない」となった場合は、事前に管轄の税務署へ相談してみましょう。(参考:国税庁|No.4424 債務免除等を受けた場合)
親子ローンを利用する(ペアローン・リレーローン)
最後の方法は、親子ペアローンやリレーローンを利用する方法です。
どちらも、子が連帯債務者もしくは連帯保証人になることで、年齢制限が引き上げられ、総融資額が増えます。
親子ともに住宅ローン控除が利用できる点もポイントです。
ただし、親子で債務ができるため、どちらか返済が難しくなった場合もお互いに援助しづらくなる点や、将来的に別居する場合の名義変更が難しくなる点は否めません。
相続時に兄弟とトラブルに発展する可能性もあるため、親子ローンを利用する際は、ご家族でじっくりご検討ください。
実家リノベーションには計画段階から綿密なシミュレーションが必要
ご両親がご健在のうちに実家リノベーションをする場合、住宅の所有者とリノベーション費用の負担者が異なるケースも多く、思わぬ出費が発生したり、いざ相続する際にトラブルになったりすることも少なくありません。
そのため、リノベーションの計画段階から、設計プランだけではなく、お金のプランニングも進める必要があります。
「家の名義変更はするべきか」「名義変更せず贈与税を支払った方がいいのか」「どんなローンを誰が契約すべきなのか」など、細部までシミュレーションして検討することがポイントです。
ただし、税法やローン商品の特徴などをご自身で調べるには、かなりの労力や時間がかかります。
そのため、ご家族で話し合いを重ねると同時に、ファイナンシャルプランナーなどプロのアドバイスを受けるのがおすすめです。
〈おすすめコラム〉
マンションをリノベーションで“二世帯住宅”にできる?多世帯で快適に過ごすポイントは?
将来に備えた実家リノベーションは幅広いサービスを受けられる“ワンストップリノベ”がおすすめ
実家リノベーションの先には、「不動産の相続」という大きな壁が待ち受けています。
その際、再びリノベーションして住み継ぐのか、もしくは売却してその資金で新居を購入するのかなど、考えなくてはいけないことは山積みです。
そこでおすすめなのが、“ワンストップリノベーション”。
私たちSHUKEN Reでは、住宅ローンや将来を見越した資金計画を相談できる「FP相談」から、多彩な施工実績のある「リノベーション相談」、住まなくなったご実家などの「物件売却」まで、それぞれの専門家がワンストップでサポートしております。
不動産売買のプロと、建築知識豊富なリノベーションのプロが、あなたの“実家リノベーション”だけではなく、その後のマイホーム計画をしっかりお手伝いいたします。
「実家をどんなふうにリノベーションすればいいか分からない」「予算がどのくらい必要か知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
中古住宅を購入してリノベする流れを解説|ワンストップの魅力とは
まとめ:実家リノベーションの資金計画はプロへの相談が必要
実家の所有者がまだご両親の場合、リノベーションの費用を誰が負担するかによって、思わぬ出費が発生する可能性もあります。
そのため、実家の名義変更も含め、総合的な検討が必要です。
しかし、税法の詳細やローンの仕組みなど、一般の方ではなかなか理解しにくい点が多い上に、リノベーションのプラン打ち合わせを進めなくてはいけないとなると、かなりの負担になってしまいますよね。
また、将来相続した時のことも考える必要があるでしょう。
“SHUKEN Re”では、今まで培った知識と経験を踏まえて、資金計画からリノベーションの設計施工、アフターメンテナンス、将来の売却相談まで、ワンストップでサポートしております。
オンラインでの無料相談も承っておりますので、「実家を今後どうしたらいいか迷っている」「実家を快適にリノベーションしたい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

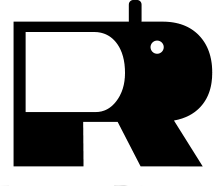










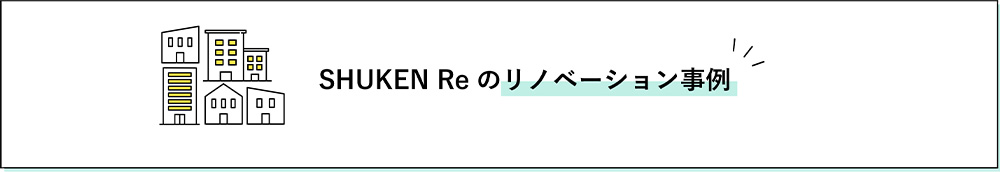
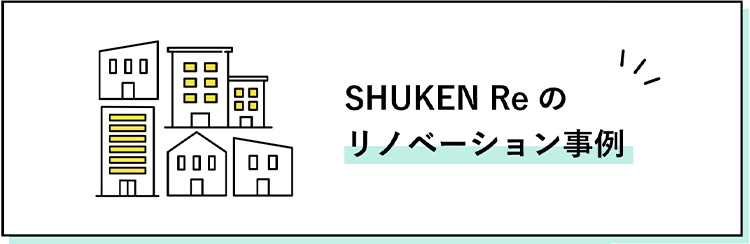







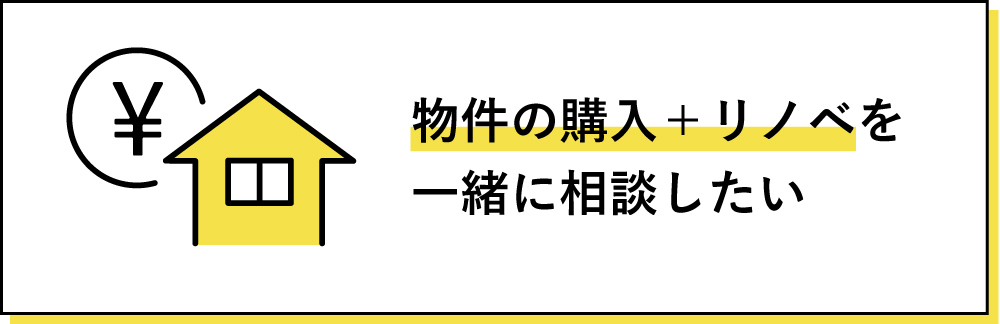
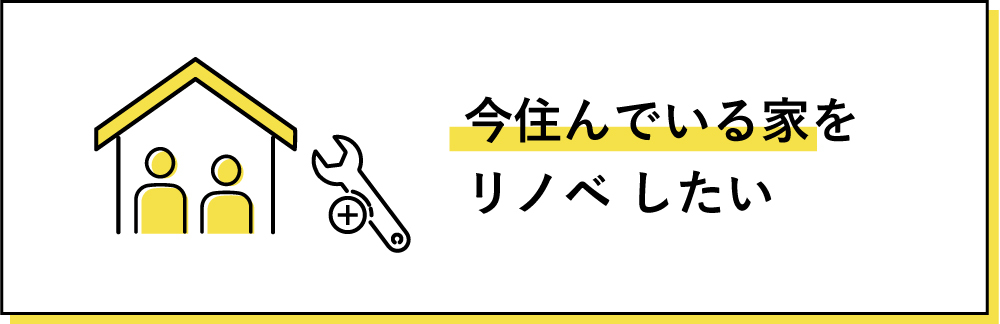
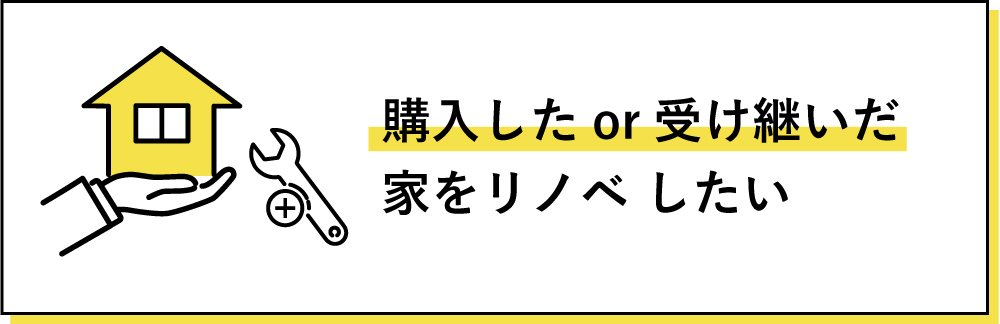
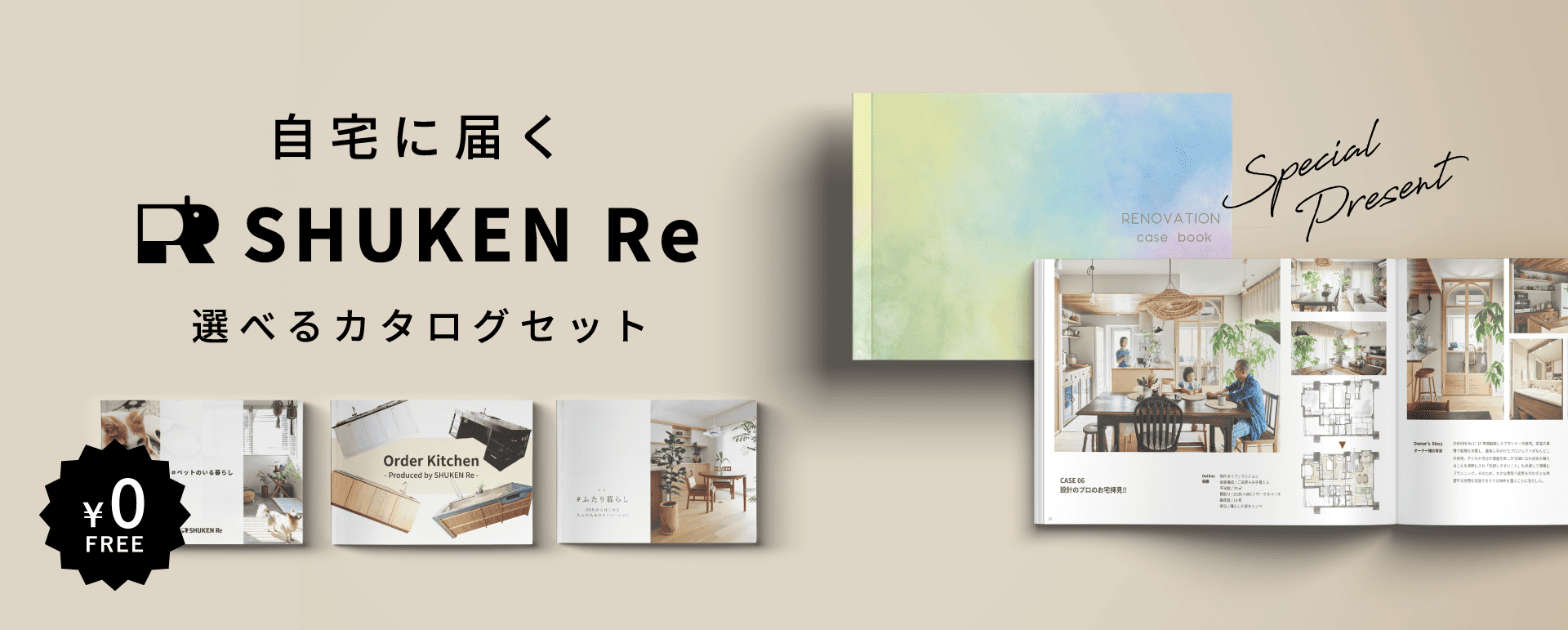



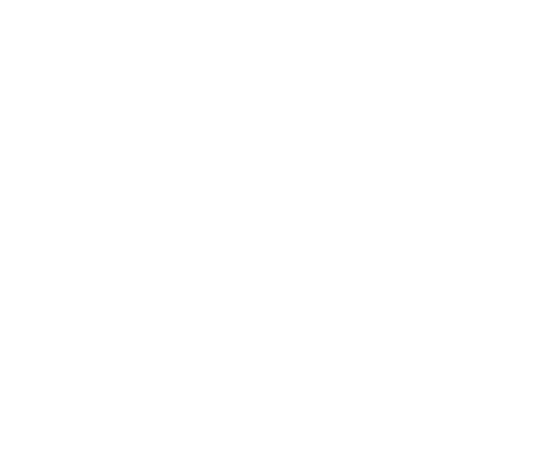





 電話で相談
電話で相談