公開日:2025-10-13
住宅ローンの借り換えで失敗しない方法|注意点と対策ポイントを分かりやすく解説

「住宅ローンの返済負担を減らしたい」「物件の融資額とリノベーション費用を1本化したい」とお考えなら、借り換えが有効な場合があります。
住宅ローンの借り換えでは、適用金利が低くなったり、団体信用生命保険の保障内容を見直せる可能性がある一方、審査や手続きの手間、手数料がかかる点にも注意が必要です。
そこで今回は、住宅ローンの借り換えを視野に入れている方向けに、メリット・デメリットや失敗しやすいケースの対策方法を整理しながら解説していきます。
約25年で8,000件超の実績があるSHUKEN Re(シュウケン・アールイー)では、FP相談(ファイナンシャル・プランニング)による、資金計画や家計の見直しもご相談いただけます♪
- ・住宅ローンの借り換えでは、金利変更にともなう返済額の軽減や保証内容の見直しなど、条件が良くなるケースがあります。
- ・審査リスクや諸費用がかかる点にも注意して、失敗しない方法を検討しておきましょう。
- ・住宅ローンの借り換えを成功させるためには、事前シミュレーションと適切なタイミングの見極めが大切です。
■住宅ローンを借り換えるメリット・デメリット

住宅ローンの借り換えでは、金利や保障内容の見直しにより、毎月の返済額や総返済額が軽減できる可能性があります。
ただし、条件次第では予想通りのメリットが得られないケースもあるため、まずは借り換えの仕組みをよく理解しておきましょう。
住宅ローン借り換えのメリット
住宅ローンの借り換えでは以下のようなメリットが期待できます。
- ・金利が低くなれば、毎月の返済額や総返済が削減できる
- ・新しい保険への切り替えで保障範囲が広がる
- ・住宅ローンの残債とリノベーション資金を借り換え時にまとめられる
- ・変動金利から固定金利への変更で、将来の金利上昇リスクが避けられる
金利の見直しを目的とした借り換えの場合、借入中の住宅ローンより低い金利タイプに変更することで、月々の返済額ないし総返済額が抑えられるため、長期的な家計負担の軽減につながります。
住宅ローンの借り換え時には、新たに団体信用生命保険(団信)*に加入する必要があり、その際、保障内容の見直しや3大疾病などにも対応する特約付き保険への切り替えも可能です。
また、住宅ローンの完済を終えていない物件のリノベーション資金を借り換え時に1本化できるのもメリットです。
一般的にリフォームローンは、住宅ローンと比べて金利が高く、団信付でないケースが多いため、それぞれ別の条件で融資を増やすよりも、借り換えでまとめた方がお得になる場合があります。
*団体信用生命保険:住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合、生命保険会社が契約者に代わり融資残高(相当分)を金融機関に支払う保険。
住宅ローン借り換えのデメリット
次に、借り換えをご検討の場合に、注意しておきたいデメリットもチェックしておきましょう。
- ・借り換え先金融機関で審査を受ける必要がある
- ・借り換え時の事務手数料や保証料、各種登記費用などの諸費用がかかる
- ・手続きのために時間や手間を要する
まず借り換えを実行するためには、金融機関による審査を通過する必要があります。
転職による勤続年数や収入の変化、年齢、健康状態、他の借入などが影響して、審査に通りづらいケースもあるため、あらかじめ施工会社の担当者に相談しておくのもおすすめです。
また審査を通過した場合でも、借り換え先金融機関での手続きに必要な借入中ローンの完済手数料や抵当権抹消・設定の登記費用、保証料などの諸費用を含め、どれくらいメリットが出るかを試算する必要があります。
これに加えて、公的証明書の発行など、必要書類の準備に一定の時間や手間がかかることも念頭に入れておきましょう。
〈関連コラム〉
住宅ローンはみんないくら払ってる?「きつい」と感じないための返済額の決め方や注意点も解説
東京・千葉・神奈川エリアで約25年にわたり、8,000件超の施工実績があるSHUKEN Reでは、中古物件購入やリノベーションに関する資金計画のご相談も受け付けています。
■住宅ローンの借り換えで失敗するのはどんなケース?

住宅ローンの借り換え計画が失敗しやすいポイントや具体例を整理してみましょう。
新規借入時より審査通過が難しい
転職などが理由で勤続年数がリセットされたり、収入が下がっている、物件の担保価値が低い場合など、審査上で不利な条件として、借り換え審査に影響する可能性があります。
また新規借入時より年齢が上がり、健康状態にも変化がある場合は、借り換え時に必要な団信の加入審査に落ちて、新たに住宅ローンが組めないケースも出てきます。
また、借り換えのタイミングで自動車ローンや教育ローンなど、他の融資が増えている場合も、収入の増加に関わらず、審査に通らないケースがあるため注意が必要です。
予想以上の諸費用がかかる
借り換えに必要な諸費用を試算に含めなかった場合、金利差による住宅ローン返済額の軽減効果が活かせない、あるいは逆効果になるケースも考えられます。
住宅ローンの借り換えには、主に以下のような諸費用がかかるため、希望する住宅ローンとの金利差によっては思うような効果が見込めない場合もあります。
- ・事務手数料
- ・保証料
- ・繰上返済手数料
- ・団体信用生命保険料
- ・抵当権抹消費用(登録免許税)
- ・抵当権設定費用(登録免許税)
- ・印紙税
- ・司法書士費用 など
事務手数料や保証料、繰上返済手数料、団体信用生命保険料などは、金融機関によって相場が変わります。
司法書士費用は、一般的に抵当権の抹消に数万円、抵当権の設定に5~10万円程度かかるのが相場です。
また、登録免許税や印紙税は以下の通りです。
| 抵当権抹消費用(登録免許税) |
土地1筆、建物1戸につき1,000円 |
|
抵当権設定費用(登録免許税)* |
借入額×税率(本則0.4%→特例0.1%) 適用期限:令和9年3月31日 |
|
印紙税
|
500万円超え~1,000万円以下:1万円 1,000万円超え~5,000万円以下:2万円 5,000万円超え~1億円以下:6万円 (電子契約の場合は0円) |
*(参考)国土交通省|住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置
金利によっては借り換え効果が薄い
金融機関では、融資実行時の金利を「借入金利」として決定するため、申し込み時の金利がそのまま適用されるわけではないことに注意が必要です。
つまり、申し込みから審査を経て、契約手続きを終え、融資実行までに月をまたぐなどして、金利が変動した場合は、予想よりも借り換え効果が得られない可能性もあります。
特に、固定金利の場合は、近年の金利変動の激しさが影響する可能性があり、想定よりも金利が高くなるシミュレーションもしておくのがおすすめです。
なお、固定金利から変動金利の住宅ローンに借り換える場合は、実行時の金利が下がっていても、借入期間中に金利上昇のリスクがあることを理解しておきましょう。
団信の保障内容によっては不利になる
借り換えにともない、新たな団信にも加入する必要があります。
その際、借り換え先の住宅ローンの団信の内容が異なり、保障の範囲が狭まる可能性もあります。
例えば、がん特約や3大疾病保障が付いているプランから、死亡や高度障害のみを対象とした団信に変更する場合は、万が一の備えが十分かどうか確認しておきましょう。
借り換えとあわせて保障内容の強化をご検討の際は、上乗せ金利による月々の上乗せ金額を試算しながら、毎月の返済額を比較するのがおすすめです。
〈関連コラム〉
旧耐震物件は住宅ローン審査が通りづらい?旧耐震マンション・戸建てでローンを組める条件も解説
中古住宅を買う際に住宅ローンは“変動金利”と“固定金利”どっちがいい? |それぞれの特徴や金利タイプの選び方を解説
■借り換えで失敗しないための対策ポイント

マンションリノベーションの事例を見る:Case211「Housekeeping」
住宅ローンの借り換えで失敗しないためには、事前の情報収集と専門家との相談、適切なスケジュール管理が欠かせません。
金融機関に借り換えシミュレーションを依頼する
住宅ローンの借り換えを検討する際は、対面相談が可能な金融機関でシミュレーションを依頼してみましょう。
試算結果は、金利差だけでなく借入中の住宅ローン残高や返済期間などによっても異なるため、借り換えに必要な諸費用を含めたトータル比較で、より効果のある最適なプランが選べます。
シミュレーションを依頼する際は、メガバンクや地銀、ネット銀行など、条件の違いを比較するのもポイントです。
また、専門家に審査結果を想定してもらうことで、借り換えを実行すべきか、あるいは見送るべきかの判断がしやすくなります。
団信の内容や特例、上乗せ金利を比較する
借り換え計画をはじめる前には、借入中の住宅ローンの団信に関する情報をあらかじめ見直しておくことが大切です。
例えば、現在の保障内容を忘れてしまっている場合、借り換えのタイミングで必要な特例を追加することができなかったり、上乗せ金利をふまえた総返済額の比較もできません。
万が一のリスクに備えながら、借り換えの効果が得られるよう、金利だけでなく団信の保障範囲もよく確認しておく必要があります。
借り換えにベストなタイミングを見極める
通常、住宅ローンの金利は融資実行の時点で決められるものですが、金融機関によっては、契約時に決定する場合もあるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
なお、残債が少ない場合や返済期間が短い場合は、借り換えによる効果が下がるケースもあるため、固定期間の終了時や金利引下げキャンペーンなど、タイミングの見極めもポイントになります。
また、固定金利か変動金利かを選び直す場合も、専門家に相談しながら、将来の金利動向を見て判断するのがおすすめです。
〈関連コラム〉
中古住宅購入・リフォームでフラット35は使える?築年数や優遇金利の条件、手続きの流れを解説
中古物件で住宅ローンを使う|新築との条件の違いや借入年数、金利、控除、物件選びのコツを解説
■住宅ローンの借り換えに関する「よくある質問」

マンションリノベーションの事例を見る:Case206「Memorable」
物件探し+リノベーションだけでなく、将来の収支を見据えたFP(ファイナンシャル・プランニング)でお客様の不安を解消するSHUKEN Reが、住宅ローンの借り換えに関する疑問にお答えします。
Q.住宅ローンの借り換えは返済何年から可能?
A.住宅ローンの借り換え可能時期や条件は、金融機関によって異なります。
一般的には、返済実績1年以上やこれまで半年から数年間の返済に問題がない場合などを条件に、借り換え申込みが可能になります。
ただし、住宅ローンの残債や返済期間によっては、好条件で借り換えできない場合があるため、あらかじめご希望の金融機関に、詳しい申し込み条件を確認するのがおすすめです。
Q.住宅ローンは同じ銀行で借り換えはできる?
A.原則として、同じ銀行で金利引き下げを目的とした借り換えはできません。
ただし、同じ銀行内でも異なる住宅ローン商品への変更や、金利タイプの見直し、繰り上げ返済などの返済条件の変更は可能な場合があります。
例えば、金融機関によってはフラット35からフラット20への借り換えは、「契約内容の変更」として認められる場合があります。
Q.住宅ローンの借り換えは何回できる?
A.住宅ローンの借り換え回数に制限はありません。
過去に借り換えした住宅ローンであっても、審査に通れば再度借り換え可能です。
ただし、その都度諸費用が発生するため、支出の増加を含めた総合的な判断が必要になります。
Q.住宅ローン控除適用期間中に借り換える場合の影響は?
A.借り換えをした場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除は引き続き適用されます。
ただし、控除期間の延長はありません。
また、借り換え後も引き続き住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
・新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
詳しくは、金融機関や施工会社の担当ファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
〈関連コラム〉
中古物件購入を検討中の方必見 |住宅ローンはどれくらい借りられる?目安額や月々の返済額はどのくらい?
住宅購入のペアローンは“やめた方がいい”の真実|メリット・デメリットと2024年減税控除
中古マンションの住宅ローン控除とリフォーム減税のポイント|2024年から変わる要件や期間をチェック
■まとめ
住宅ローンの借り換えでは、金利タイプの変更や好条件なタイミングによって、今後の返済が有利になる可能性があります。
また、借入中の住宅ローンとリノベーション資金を借り換えのタイミングで1本化する場合は、リフォームローンよりも低い金利で団信付が適用されるのがメリットです。
借り換えで成功するためには、残債1,000万円以上、返済期間10年以上で、1%前後金利が下げられそうなプランを基準に検討するのがおすすめです。
ぜひ、専門家によるサポートを受けながら、団信の保障内容の確認や諸費用の増加をシミュレーションに加えて、借り換えの効果を総合的に判断してみましょう。
SHUKEN Reの「FP相談」を利用したお客様からは、「想定より高い予算のマンション購入でしたが、ライフプランを元にした将来の収支についても丁寧なアドバイスがもらえて満足」との声をいただいています。
SHUKEN Reでは、リノベーションに精通したスタッフが、ご家族の希望予算や生涯のキャッシュフローを整理しながら、将来を見据えた資金計画をサポートしています♪
東京・千葉・神奈川エリアで約25年8,000件以上の経験・実績を活かして、ご家族のライフプランから本当に必要なものを明確にし、暮らし改善の方法や家計快適化のコツをご提案いたします。
浦安本店・世田谷店・青山店にショールームを併設。見学会・セミナー・相談会などのイベントも随時開催中です。
お気軽にお近くの店舗へご相談ください。

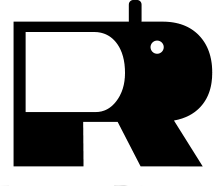










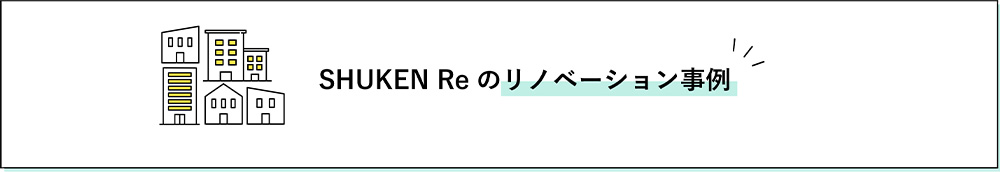
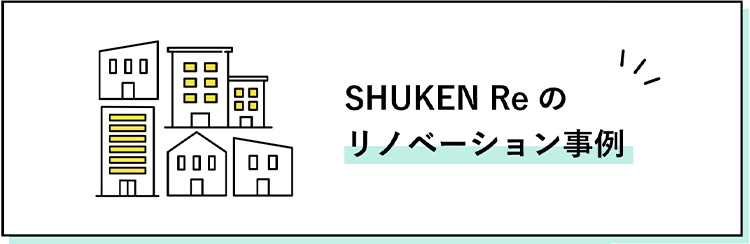

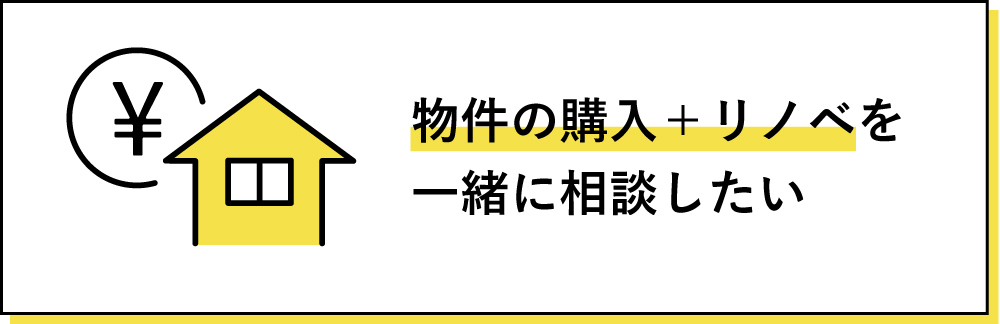
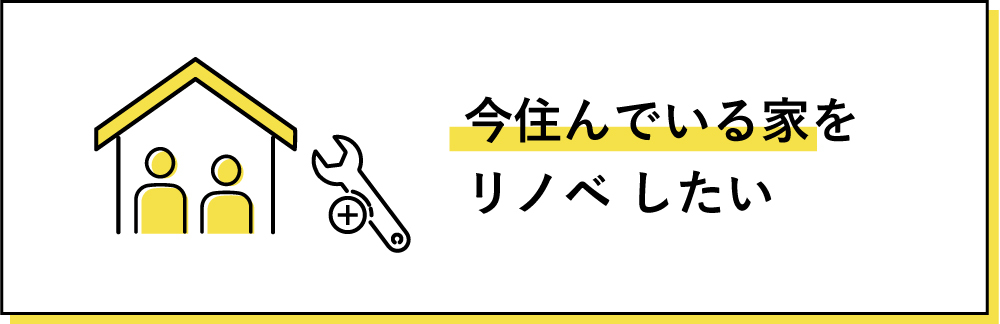
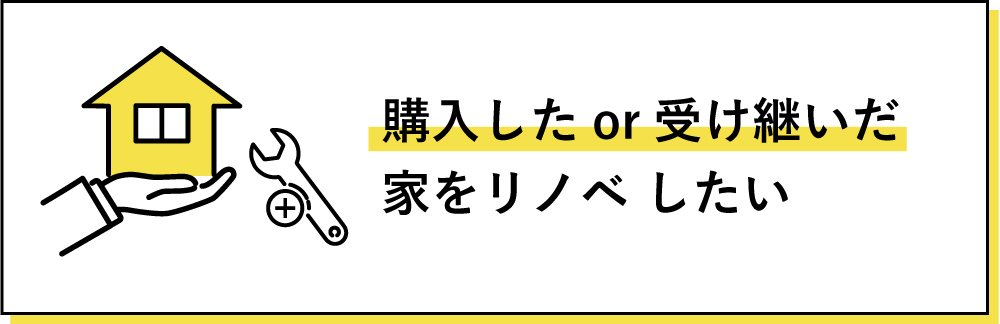
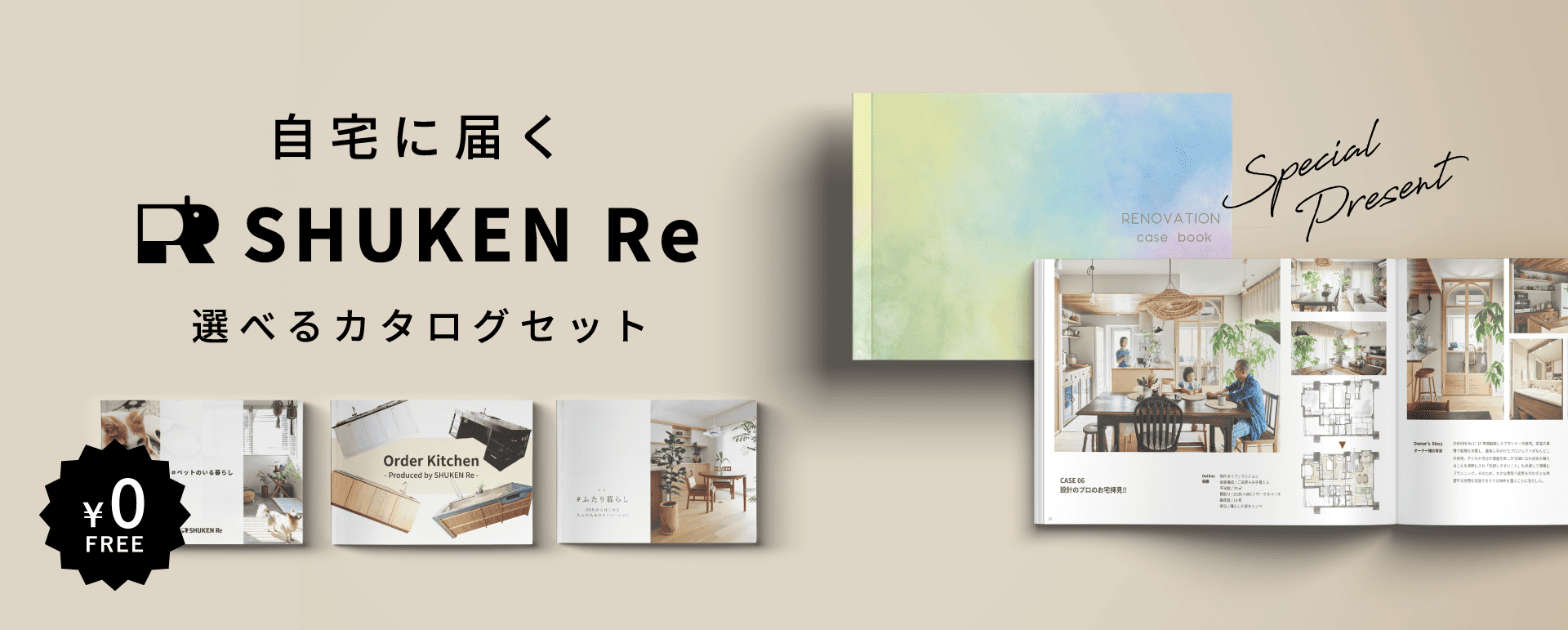



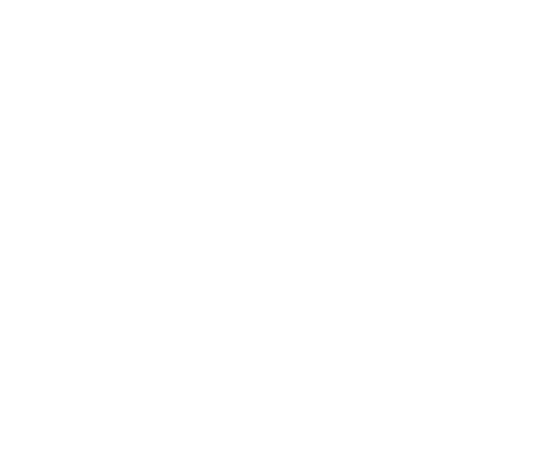




 電話で相談
電話で相談