公開日:2025-09-30 更新日:2025-11-07
寺民泊開業のメリット|宿坊との違いや成功のポイントを解説

近年、お寺の建物の一部を民泊施設として活用し、観光客に宿泊サービスを提供するケースが増えています。
お寺を民泊として活用することで、檀家からのお布施や寄付以外の収入源の確保、仏教文化の発信などさまざまなメリットが生まれます。
しかし、実際に寺民泊を開業するにあたり、どのような準備や計画が必要なのか疑問に感じる方が多いようです。
そこでこの記事では、寺民泊を開業するために必要な基礎知識を分かりやすくまとめて解説します。
寺民泊を開業するメリットや成功のポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- ・寺民泊とは民泊新法による宿泊サービスのことで、法規制や手続きのハードルが低く開業しやすいなどメリットがあります。
- ・民泊によってお寺に観光客を呼び込むことで、収益源の確保や仏教文化の発信などさまざまなメリットが生まれます。
- ・ターゲットユーザーやコンセプトを明確にする、集客方法を検討するなど、寺民泊を成功させるためのポイントを押さえておきましょう。
■寺民泊とは?

まずは、寺民泊とはどのようなサービスなのか、基本的な仕組みについて把握しておきましょう。
寺×民泊新法による宿泊サービス
寺民泊とは、民泊新法(住宅宿泊事業法)によってお寺の一部を宿泊施設として貸し出すサービスのことです。
2018年に民泊新法が施行されたことで、従来の旅館業法とは異なる枠組みで宿泊事業を営むことが可能になり、お寺を宿泊施設として活用しやすくなりました。
旅館業法における「簡易宿所」でも民泊と同じような宿泊サービスは提供できますが、お寺によっては基準をクリアできず営業許可を受けられないケースもありました。
こちらのコラムで民泊の基本的な仕組みについて解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
〈関連コラム〉
民泊の始め方を5ステップで分かりやすく解説|民泊経営を成功させるポイントも
宿坊と寺民泊の違い
昔からお寺に設置されている宿坊と民泊の違いについて明確にしておきましょう。
|
宿坊 |
僧侶や檀家、参拝者のための宿泊施設。 |
|
民泊 |
一般観光客を受け入れるための宿泊施設。 |
本来の宿坊は、修行を行っている僧侶や檀家、遠方からの参拝者が宿泊するための施設です。
一方民泊は、一般観光客に対して宿泊サービスを提供し、観光拠点や文化体験などを目的とした施設です。
近年は宿坊を民泊施設として一般観光客に開放しているお寺も増えており、明確に区別されないケースも増えています。
寺民泊が注目されている背景
近年民泊サービスを提供するお寺が増えていて、宿泊先としても注目が集まっている背景としては、次のような理由が挙げられます。
※寺民泊が注目されている背景
- 寺院の空きスペースが増加している
- 民泊が新たな収益源になる
- 地域活性化や仏教文化との接点の重要性が増している
- インバウンド需要の増加で寺が観光資源になっている
少子高齢化による檀家の減少や後継者不足といったお寺の課題と、国内外の観光需要が高まっている状況がマッチし、寺民泊に注目が集まっています。
次の章から、寺民泊を営むことでどんなメリットが生まれるのか1つずつチェックしていきましょう。
■寺民泊を開業するメリット

お寺で民泊を開業することで、次のようにさまざまなメリットが生まれます。
収益による運営の安定化
寺民泊では一般観光客からの宿泊料によって収益を得ることができ、運営の安定化が期待できるのがメリットです。
近年は、少子高齢化や檀家の減少により、収益が減少するお寺が増えています。
民泊事業によって新たな収入源を得ることで、お寺の経営安定化につなげることができます。
立地や環境を活かした競合との差別化
お寺ならではの立地や環境を活かした民泊サービスを提供することで、競合物件との差別化を図りやすいのも大きなメリットです。
歴史的価値のある建物や四季を感じられる境内の景色は、一般的な民泊施設にはない魅力として集客力を高めてくれます。
また、観光スポットが隣接する立地なら、観光拠点としての利便性が高く宿泊先として選ばれる可能性が高くなります。
新たな観光拠点として地域を活性化
民泊施設としてお寺に観光客を呼び込むことで、地域全体の活性化が期待できるのもメリットの1つです。
例えば、歴史的価値のある建物や境内の景色など、民泊を利用した観光客がSNSなどで発信することで新たな観光スポットになるケースもあります。
寺民泊がきっかけで地域が活性化すれば、魅力的なサービスが増えてさらに観光需要が増加する好循環も期待できます。
仏教文化発信の拠点として新しい出会いをつくる
民泊施設としてお寺に観光客を呼ぶことで、仏教文化発信の拠点として新たな人との接点をつくることができるのもメリットです。
檀家以外の新たな人に仏教文化を発信することで、仏教離れや檀家の減少といったお寺が抱えている課題の解決につながる可能性もあります。
■寺民泊を成功させるポイント

前述したように寺民泊にはさまざまなメリットがありますが、ただ開業しただけで安定した集客や収益が期待できるとは限りません。
寺民泊を成功させるための考え方のポイントを詳しく見ていきましょう。
ターゲットユーザーとコンセプトを明確にする
寺民泊の開業計画を立てるときは、まずターゲットユーザーとコンセプトを明確にするところからスタートしましょう。
例えば、国内の観光客が多いのか、外国人が多い立地なのかによって、適切なコンセプトや施設づくりのポイントは変わってきます。
公共交通機関、自家用車など、どのような方法でユーザーが訪れるのかなども明確にすべきポイントです。
具体的な経営計画を立てる前に、地域性や寺院の強み・特徴などを踏まえて、ターゲットユーザー像とコンセプトをつくりこみましょう。
複数の集客方法でユーザーにアプローチする
寺民泊は、ターゲットユーザーに合わせて集客方法を選び、ユーザーにアプローチすることも成功のポイントです。
例えば、オンライン旅行会社であるOTA(Online Travel Agent)に掲載して集客する場合、外国人観光客にアプローチするならAirbnbやBooking.com、国内向けならじゃらんや楽天トラベルなど、ユーザー層によって使い分ける必要があります。
また、SNSでお寺の魅力を発信したり、SEO対策で地域の観光について調べているユーザーにアプローチしたりする方法もあります。
前述したターゲットユーザーやコンセプトに合わせて適切な集客方法や広告宣伝の手法を選び、効率的に集客しましょう。
稼働時期の調整
お寺で民泊新法における民泊施設を開業する場合は年間営業日数が180日に制限されるため、需要が高い時期に絞って稼働することも成功のポイントです。
閑散期や平日など宿泊需要が少ないタイミングは稼働率が低く、固定費の方が高く赤字になってしまう可能性が高くなります。
お盆や年末年始などの観光ハイシーズン、週末などに稼働時期を調整することで、限られた営業日数の範囲内で効率的に収益を上げることができます。
また、立地が良い、お寺自体の集客力が高いなど収益性が期待できる場合は、年間営業日数の上限がない旅館業法による簡易宿所として開業するのも1つの考え方です。
外国語対応や利用ルールの策定
民泊は外国人観光客の利用が多い傾向があるため、ホームページや施設の外国語対応、利用ルールの策定なども必要です。
特に、日本と生活習慣が異なる文化圏の利用者が居る場合は、騒音や施設の使い方などでトラブルになるケースが多いので要注意。
お酒や食事の持ち込み、部屋での過ごし方など、実際の利用シーンを想定してルールを細かく決めておくことが大切です。
ただし、実際に民泊施設を運用しないと分からないポイントもありますので、施工実績が豊富な会社に相談し適切なアドバイスを受けるのがおすすめです。
体験ツアーやサウナなど魅力的なサービスを展開
ただ境内に泊まれるだけの民泊施設をつくるのではなく、お寺ならではの環境を活かして魅力的なサービスを組み合わせるのも成功のポイントです。
例えば、座禅や写経など、仏教文化に触れることができる体験ツアーは寺民泊でも人気のサービスです。
また、境内にサウナを設置して、水風呂の代わりに滝行を組み合わせるのも1つのアイデア。
宿坊や境内のリノベーションによって、お寺の特徴や強みを活かした魅力的なサービスを考えてみましょう。
こちらのコラムで寺リノベーションのアイデアについて詳しく解説しています。
〈関連コラム〉
寺リノベーションとは?改修や建て替えとの違い、費用の考え方やアイデアを解説
■寺民泊でよくある質問

寺民泊の開業を検討する際、よくある質問をまとめました。
Q.寺民泊の収益は課税される?
A.原則的に課税対象となります
寺民泊で宿泊者から受け取った宿泊料は、収益事業とみなされ課税対象となります。
宗教法人であるお寺の宗教活動自体は基本的に非課税ですが、寺民泊はそれ以外の収益事業に分類されます。
確定申告が必要になりますので、経営計画の段階で準備をしておきましょう。
Q.寺民泊のデメリットは?
A.利用者のマナーや収益減少など注意すべきポイントもあります
お寺は一般的な宿泊施設とは異なる点が多く、次のようなデメリットにも注意が必要です。
※寺民泊のデメリット
- 騒音やマナー違反など利用者と近隣住民のトラブル
- 檀家からの反対や意見の食い違い
- 閑散期の収益減少
- 運営・管理コストがかかる
民泊開業によって一般観光客を受け入れることで、お寺の品格が落ちたり近隣住民や檀家とのトラブルが発生したりするリスクが考えられます。
また、寺民泊の運営や管理には人員や金銭的なコストがかかり、収益減少による赤字のリスクもあります。
お寺施設の一部としてのバランス、収益事業としての確実性など、さまざまな点に配慮してデメリットやリスクに対策しましょう。
Q.宗教法人以外でも寺民泊を開業できる?
A.後継者が居ない寺を購入し民泊開業することは可能です
住職やお寺関係者以外の方でも、後継者が居ないお寺を購入して民泊施設として開業することは可能です。
近年は後継者不足や経営難によって住職が居なくなったお寺が、一般公開で販売されるケースが増えています。
実際、宗教法人格を持たない方がお寺を購入し、飲食や民泊などの宿泊サービスを開業するケースもめずらしくありません。
築年数が古いお寺でも、リノベーションによって魅力的な民泊施設をつくることができますので、ぜひ検討してみてください。
■まとめ
寺民泊は貴重な収益を確保できるだけでなく、仏教文化を発信したり地域活性化に貢献したり、さまざまなメリットがあり注目されています。
ただし、ただお寺で民泊を始めるだけで成功するわけではありませんので、今回ご紹介したポイントについてしっかり検討してみてください。
また、寺院での民泊開業は、一般的な住宅や宿泊施設とは異なる点にも配慮が求められます。
なるべく民泊施設づくりや寺院改修などの施工実績が豊富な会社に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けるのも成功のポイントです。

SHUKEN Reは、東京・神奈川・千葉の首都圏エリアを中心に、多くの民泊施設づくりや寺院改修の実績を持つ専門店です。
お寺の状況やご予算などを踏まえたプランのご提案、一棟まるごとリノベーションにも対応いたしますので、どんなこともお気軽にご相談ください。

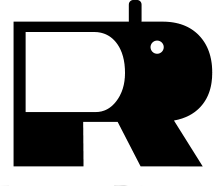










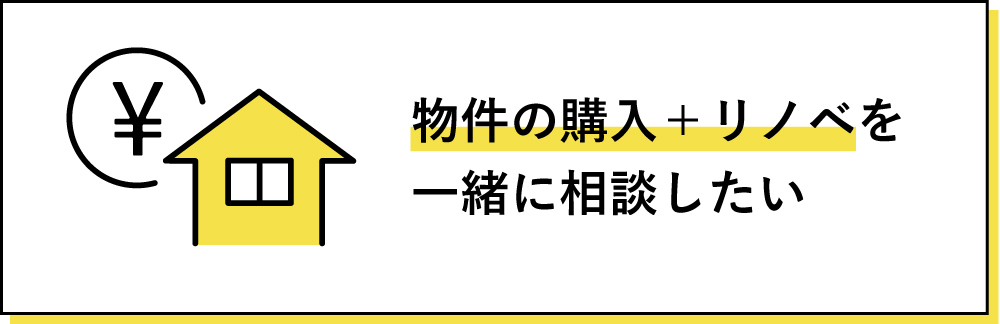
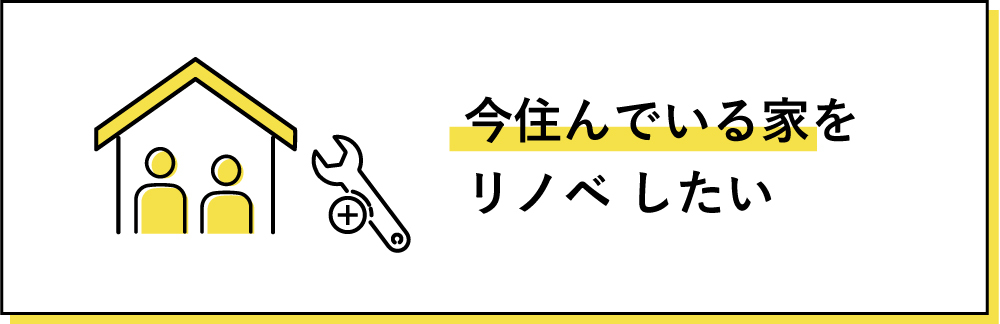
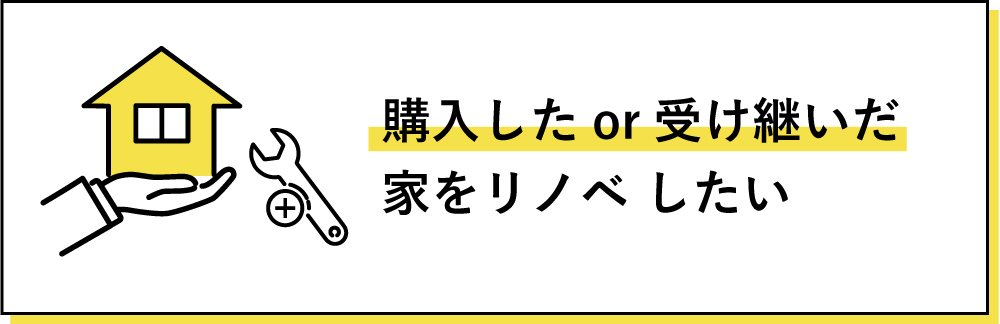
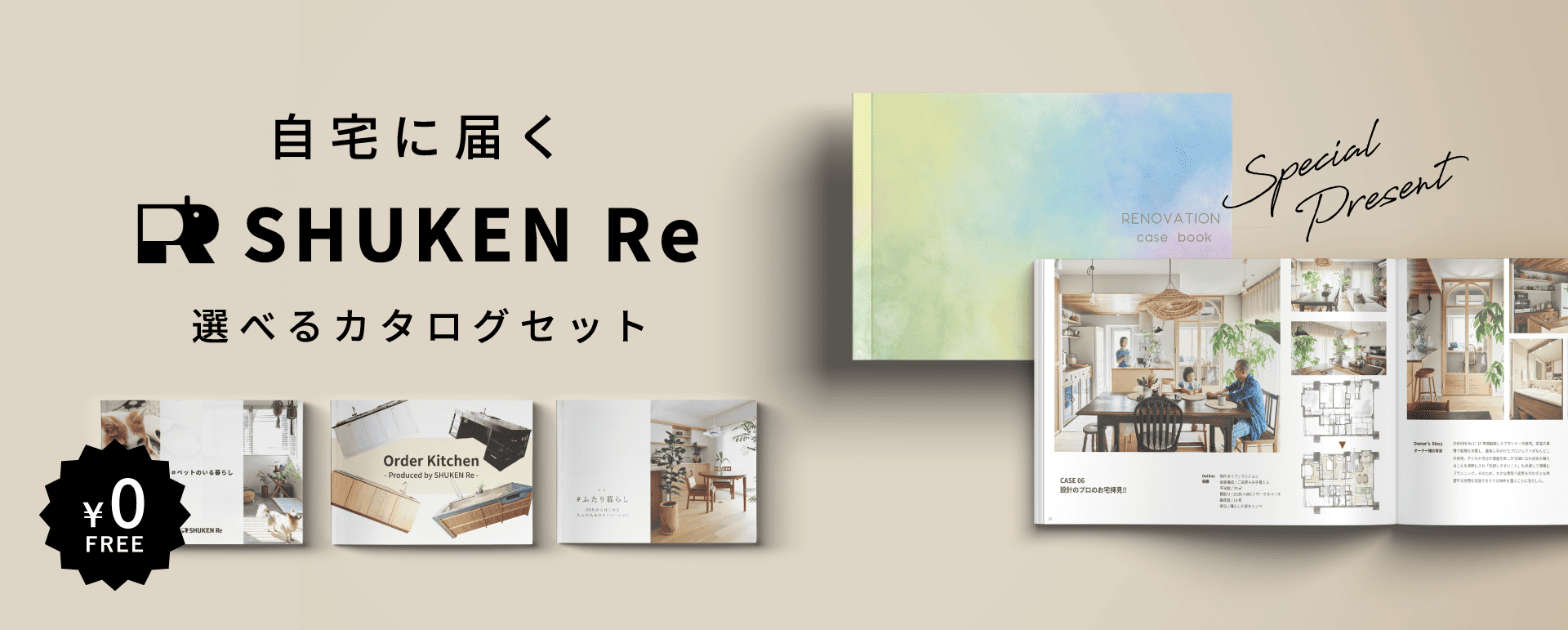



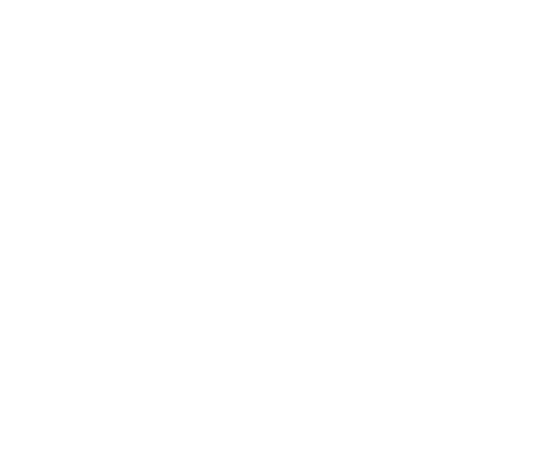




 電話で相談
電話で相談